|
|
■「外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置」事件(東京高裁 H14.4.11 平成12年(行ケ)第65号) |
医療行為の発明につき産業上の利用可能性が否定された事例
●事件の概要
原告は、「外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置」の特許出願が、医師や医師の指示を受けたものが「人間を診断する方法」であって、「医療行為」に係る発明であるから、特許法29条1項柱書にいう「産業」に該当せず、「産業上利用することができる発明」に当たらないという理由で審判において拒絶されたため、東京高裁に審決取消訴訟を提起した事件。
●裁判所の判断
医療行為そのものにも特許性が認めると、現に医療行為に当たる医師にとって、少なくとも観念的には、自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在するということになる。しかも、一般に、ある行為が特許権行使の対象となるものであるか否かは、必ずしも直ちに一義的に明確になるとは限らず、結果的には特許権侵害ではないとされる行為に対しても、差止請求などの形で権利主張がなされることも決して少なくないことは、当裁判所に顕著である。医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為に当たらなければならないことになりかねない。
特許法は、1条において、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定し、29条1項柱書きにおいて、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定しているものの、そこでいう「産業」に何が含まれるかについては、何らの定義も与えていない。また、医療行為一般を不特許事由とする具体的な規定も設けていない。そうである以上、たとい、一般的にいえば、「産業」の意味を狭く解さなければならない理由は本来的にはない、というべきであるとしても、特許法は、上記の理由で特許性の認められない医療行為に関する発明は、「産業上利用することができる発明」とはしないものとしている、と解する以外にないというべきである。
以上のとおりであるから、本願発明は、特許性の認められない医療行為に当たることが明らかであるということができ、原告の取消事由は、理由がなく、審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって、本訴請求を棄却する
|
|
|
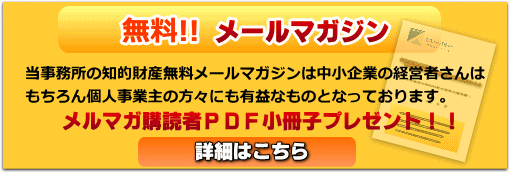
|
|

