|
|


特許(権)というと、なんだか難しそうだなって思われるかもしれませんが、そんなに堅苦しく考える必要はありません。日用品の特許の場合、基本的には、今までにはない日用品であって、今まで知られていたものでは想像できなかったような効果(新しい使い方や、便利さ)が得られるようなものであれば、特許の対象となり得るのです。
具体的には、以下のようなものです。
(例1)特許第4263809号
「洗濯用ネット及びその製造方法」
詳細はこちら→例1
(例2)特許第4012157号
「ゴム芯入り組紐リング及びその製造方法」
詳細はこちら→例2
(例3)特許第4012112号
「お玉」
詳細はこちら→例3
(例4)特許第4274486号
「携帯用歯ブラシ」
詳細はこちら→例4
(例5)特許第3932460号
「箸の補助具」
詳細はこちら→例5
(例6)特許第4029096号
「浴槽浮遊物吸着具」
詳細はこちら→例6
(例7)特許第3268897号
「モップ」
詳細はこちら→例7
(例8)特許第428795号
「泡立て器及びその製造方法」
詳細はこちら→例8
(例9)特許第4130011号
「マウスパッド」
詳細はこちら→例9
| 著作権との違い(ソフトウェアを保護する手段−特許と著作権) |
ところで、ソフトウェアを保護する手段としては、特許権と著作権があります。
特許権も著作権も、知的活動の結果、新しく作り出した物(創作物)に与えられます。
特許権は、「アイデア」を保護の対象にしており、非常に強い独占的な権利になっていますが、出願しなければ、権利が付与されることはありません。
これに対して、著作権は、「表現」を保護の対象にしており、登録しなくても創作した時点で権利が発生します。また、同一の対象であっても複数の権利が発生することがあり得ます。
具体的には、コンピュータのアルゴリズム(コンピュータを使ってある特定の目的を達成するための処理の手順)は、特許権の対象となりますが、コンピュータのアルゴリズムをより具体的な手順として表現したプログラムリストは、特許権の保護対象とはならず、著作権の保護対象となります。
ここで、一つのアルゴリズムに対して、プログラムリストは、極端な話、無数にあることとなります。
例え話をするならば、
「東京から京都を経由して大阪に向かう経路」……アルゴリズム
「東京から京都を経由して大阪に向かう一つの経路」……プログラムリスト
と考えることができます。
したがって、プログラムリストに沿って処理を実行すると、アルゴリズムを実行することになりますが、逆は成り立ちません。
この場合に、対応する道路を利用した人から通行料を取る場合に、どちらがより多くの通行料を取ることが可能となるかは考えてみるまでもないことです。
すなわち、どちらがより多くの第三者に影響を与える権利(より強い権利)であるかは明白であり、特許権が著作権よりも強い権利であることは自ずと明らかですよね。
|
|
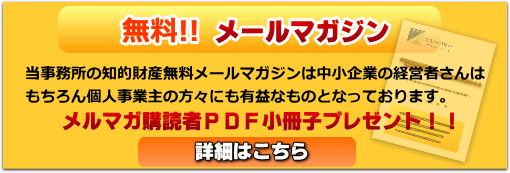
|
|







